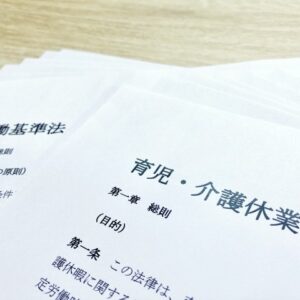なぜ就業規則の見直しが必要か
中小企業の経営を守るルール整備の第一歩
1. はじめに
就業規則とは、会社と従業員との間の「約束ごと」を定めたルールブックです。労働時間、休日、賃金、懲戒など、職場における基本的なルールが明文化されており、企業運営におけるトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
特に中小企業では、限られた人材や資源の中で安定的な経営を行うためにも、就業規則の整備と定期的な見直しが欠かせません。
2. 就業規則を見直すべき主な理由
2-1. 法改正への対応
近年、「働き方改革」や「育児・介護休業法改正」など、労働関係法令は頻繁に改正されています。例えば、2025年の法改正では、育児介護休業法が改正され育児期の柔軟な働き方を実現するための措置が義務化されました。こうした変更を反映しないまま放置すると、法令違反となるリスクがあります。
厚生労働省や労働局のホームページでも、法改正情報やモデル就業規則が掲載されており、これらに沿った対応が求められます。
2-2. 働き方の多様化への対応
テレワーク、副業・兼業、フレックスタイムなど、働き方は多様化しています。これらに就業規則が対応していないと、制度導入時に混乱が生じたり、従業員との間でトラブルになることがあります。
特に副業を認める場合は、就業規則に明確なルールを設け、労働時間や機密保持との兼ね合いを整えることが重要です。
2-3. 労使トラブルの未然防止
懲戒処分や解雇に関する規定があいまいだと、不当解雇と主張されるリスクがあります。日本年金機構や労働局の相談窓口にも、そうした労使紛争の相談が多く寄せられています。明確で最新の就業規則は、万が一の際の会社の防衛策となります。
2-4. 社内制度や実態とのズレ修正
制度改定や給与体系の変更などを行っても、就業規則を放置していると、現場とのズレが生じ、従業員の不満や混乱を招きます。「ルールと現実が一致していない」状態は、企業の信頼性にも影響します。
3. 見直しを怠った場合のリスク
- 労使紛争に発展するおそれ
不明確な規定が原因で従業員とトラブルになり、裁判に発展するケースもあります。 - 労働基準監督署からの是正指導
未整備の就業規則や法改正に未対応の内容は、監督署の調査で指摘されることがあります。 - 従業員のモチベーション低下
制度の整備が行き届いていない職場では、従業員の働きやすさが損なわれ、離職にもつながりかねません。
4. 見直しのタイミングとポイント
- 法改正があったとき
法改正に伴う義務や手続きの変更に合わせて就業規則も更新しましょう。 - 組織・制度の変更時
賃金制度の改定、人事制度の見直し、テレワーク導入などの際には、就業規則の整合性を確認する必要があります。 - 定期的な見直し(例:3年ごと)
変更がない場合でも、法令や社会情勢を踏まえて定期的に内容を見直すことが望ましいです。
5. 社会保険労務士の活用と専門家のサポート
就業規則の見直しは、単なる文章の修正ではなく、法令・判例・実務運用への深い理解が必要です。
社会保険労務士(社労士)は、厚生労働省や健康保険組合の制度動向にも通じており、企業に合った制度設計を提案できます。
専門家の支援を受けることで、リスクを最小限に抑えつつ、会社の実態に即した就業規則を整備することが可能です。
6. まとめ
就業規則は、企業と従業員の関係を支える「ルールの柱」です。変化する社会や法制度に合わせて、定期的な見直しを行うことが、トラブル予防・企業の信頼向上・社員の定着強化につながります。
「うちは小さな会社だから…」と放置せず、ぜひ一度、専門家と一緒に見直してみてはいかがでしょうか。